謹賀新年
謹んで新春をお祝い申し上げます。
昨年は、当ブログの開設、運用の開始を行い、個人的にもいろいろと実験を行う日々でした
・AI系のサービスの利用やその発信
・AI系サービスの利用を通じて得られた注意するべき点の発信
・そもそもITサービスとしての利用方法の発信
これらを本業やトライアスロンロングのトレーニングの合間を縫って行ってきました。
挑戦初年となる昨年はなかなか時間が取れず、あらかじめ作っていた記事もすぐに底をつきなかなか思うように発信ができない日々が続いてしまいましたが、その間にもいろいろ調査や実験を進め情報を集めてきました。特に苦手となる物書きやデザイン系の下記サービスの生成AIの利用に取り組んできます
- Copilot
- Canva
- Mootion
Canvaは有名なデザインアプリで、すでに個人のInstagramの更新にも実は利用しています。
Mootionは新興の生成AIサービスでこちらもSNS運用の大きな手助けとなるツールになること間違いなしというものなので、活用と発信を行えればと考えています。
ちょっとずつにはなりますがこれらの発信も進めていきたいと思います。
また今年中にはこれまでの機械学習・統計・AI・システム開発の知見をフルに活用した一つサービスをリリースを計画していますので、楽しみにしていてください。
この後は、自戒も込めて今年の目標を一つ一つのセクションごとにまとめたいと思います
セキュリティと聞いて思い浮かべるもの
「セキュリティ」と聞いて、まず思い浮かべるのは何でしょうか。多くの人が、暗号化技術や仮想化、ファイアウォールといったIT技術を想像するのではないかと思います。確かに、現代の情報社会において、これらの技術はセキュリティの中核を担っています。
しかし、こうした技術はあくまで「道具」に過ぎません。真に問われるべきは、それを扱う「人」の意識と行動です。セキュリティとは、技術だけで完結するものではなく、人の文化や態度に深く根ざした問題なのです。
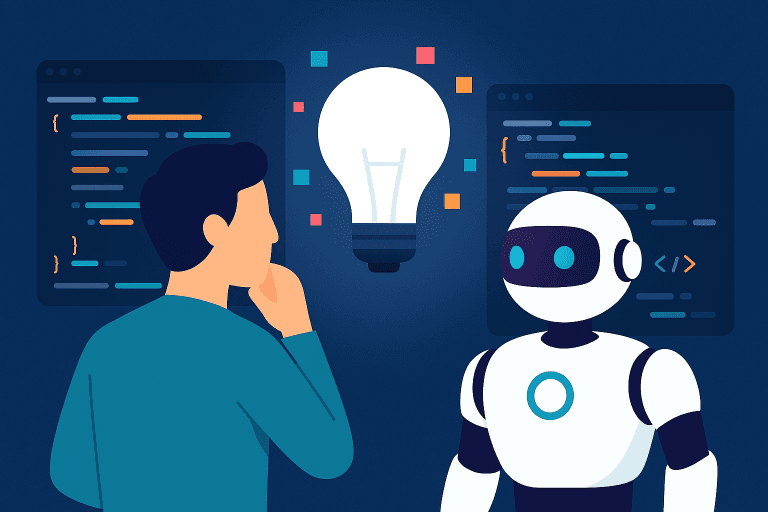
生成AIは「打ち出の小づち」ではない
「GitHub Copilot使えば、プログラミング知識なくても開発できるらしい」 「ChatGPTに頼めば、コード書いてくれるから楽だよね」
こういう話、最近よく聞きませんか?
確かに、生成AIは驚くほど高品質なコードを生成してくれます。私も日
常的にGitHub Copilotを使っていて、その便利さは身をもって実感しています。
でも、それは「打ち出の小づち」ではありません。
今回、Next.js 15で作っているブログサイトに、PC版のサイドバーを追加するという、ごく普通のタスクをCopilotと一緒にやりました。要件はシンプル。「記事一覧ページにあるサイドバーを、記事詳細ページにも追加する」。ただそれだけ。
結果として、3回やり直しになりました。
「サイドバー追加して」→ 位置が逆 「位置を左に」→ まだ何か違う 「記事一覧と同じレイアウトに」→ ようやく完成
ビルドは毎回通ります。表示も一見問題ありません。でも、細かい部分で「何か違う」が積み重なっていました。
この経験を通じて痛感したのは、生成AIでのコーディングには、設計の知識や運用経験が絶対に必要だということ。
AIが生成したコードが「動く」ことと、それが「正しい設計」であることは、まったく別の話です。その違いを見抜けないまま開発を進めると、後で取り返しのつかない技術的負債を抱えることになります。
これが、生成AI時代のコーディングの現実です。
今日は、この「打ち出の小づち」神話を解体しながら、AIとどう向き合うべきか、実際の体験をもとに書いていきます。
広告
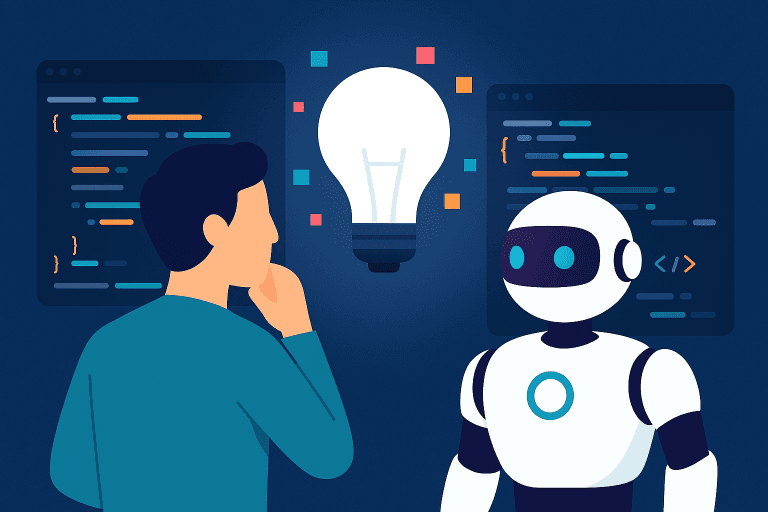
はじめに
ブログやメディアサイトを運営していると、広告ネットワークの導入は収益化の重要な一歩です。
Webエンジニアであれば何度も行ってきたであろう広告の導入で、今回も数時間で終わるだろうと思っていましたが、非同期処理ではまり、二日間を要しました。
今回は、Next.js(App Router構成)で日本の広告ネットワーク「AdStir」のバナー広告を導入しようとした際の、実装・トラブル・解決までの記録をまとめました。
この記事のポイント
- Next.js(SPA)で広告タグを埋め込む際のトライ&エラー
- CSP(Content Security Policy)との格闘
- Hydration Errorやdocument.writeの罠
- 最終的に「非同期タグ」が必要だった理由とその発見プロセス
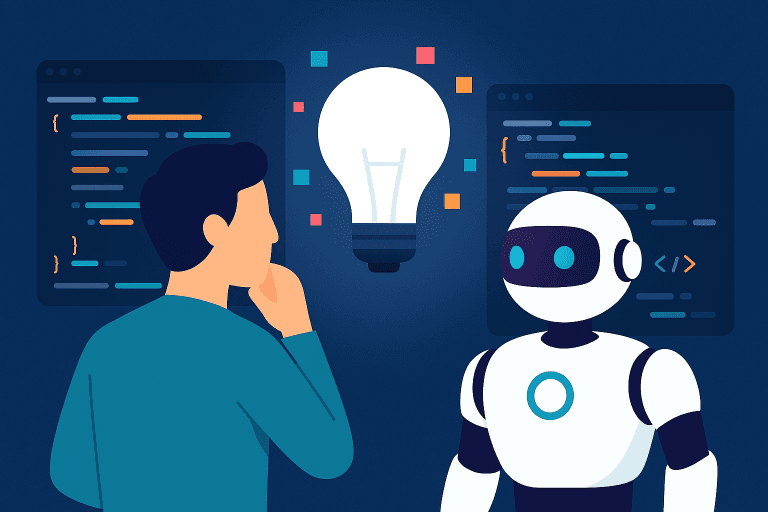
はじめに
「AIがあれば、もう人はいらないんじゃないか?」
そんな声を聞くことが増えた昨今。ChatGPTやGitHub CopilotのようなAIツールが登場し、コードを書くスピードは飛躍的に向上しました。私自身も、子育てを始めてからというもの、限られた時間の中で開発を進めるためにAIコーディングを積極的に活用しています。
しかし、子育てと仕事を両立する中で、ある日ふと気づいたのです。「AIは、指示がなければ動かない」という、当たり前だけど見落としがちな事実に。
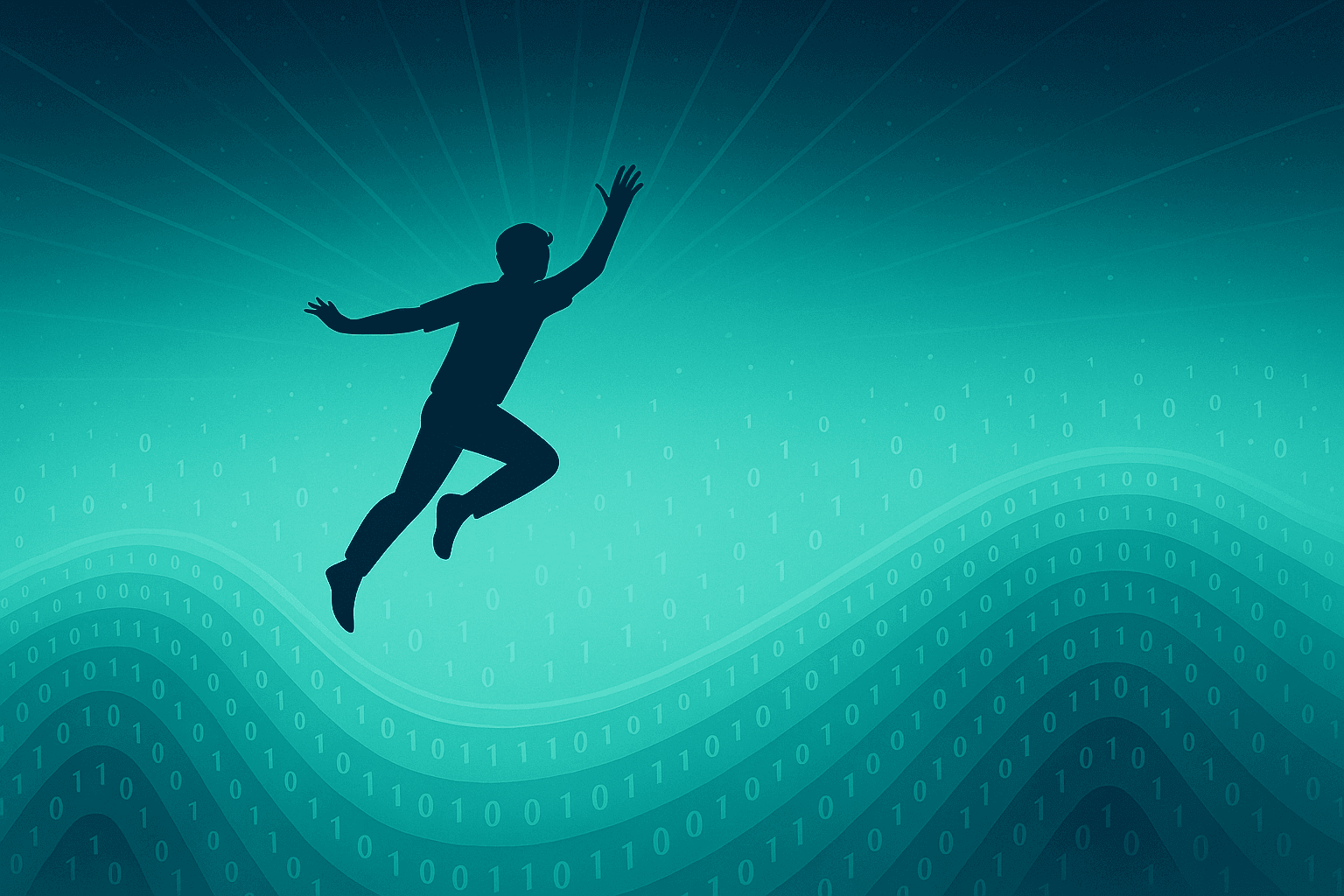
コラム:データの読み方
データ駆動、データを基にした意思決定。。。
古くはAlibabaやSpotifyが得意としてきました。最近はラーメンの山岡家も活用しているデータ。
現場にいるとこのデータの読み方がいまいち苦手な方が多くいらっしゃいます。
私自身まだ「AI」という言葉がここまで浸透する前に自然言語ベースのレコメンドエンジンを武器として、おすすめ記事のCTRを50%上昇させた経験があります。
データとは何か一緒に考えていきましょう
広告
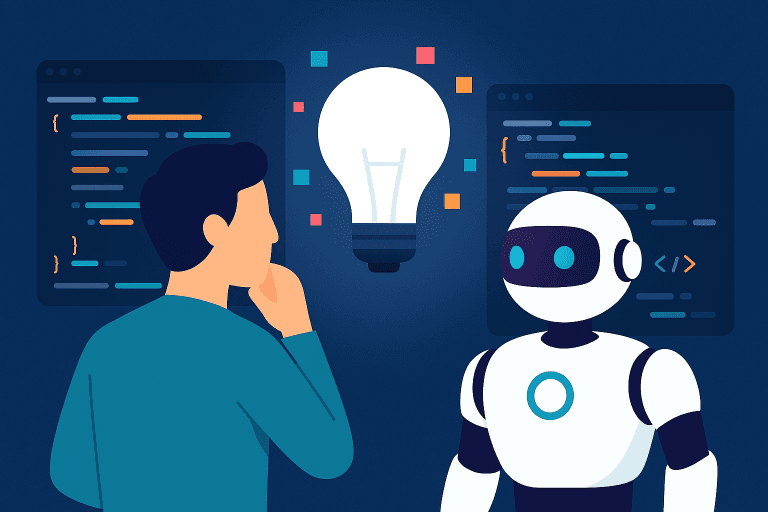
Github Copilotは優秀なAIエージェント
Github Copilotを使えばコーディングが一人でも比較的軽快に進む。
これは以前の記事で示した通りです。
しかし、「銀の玉」はありません。銀の玉はすべてを解決してくれるものという意味ですが、そういう代物ではありません。開発を通じてわかったことをいくつか書いていきます
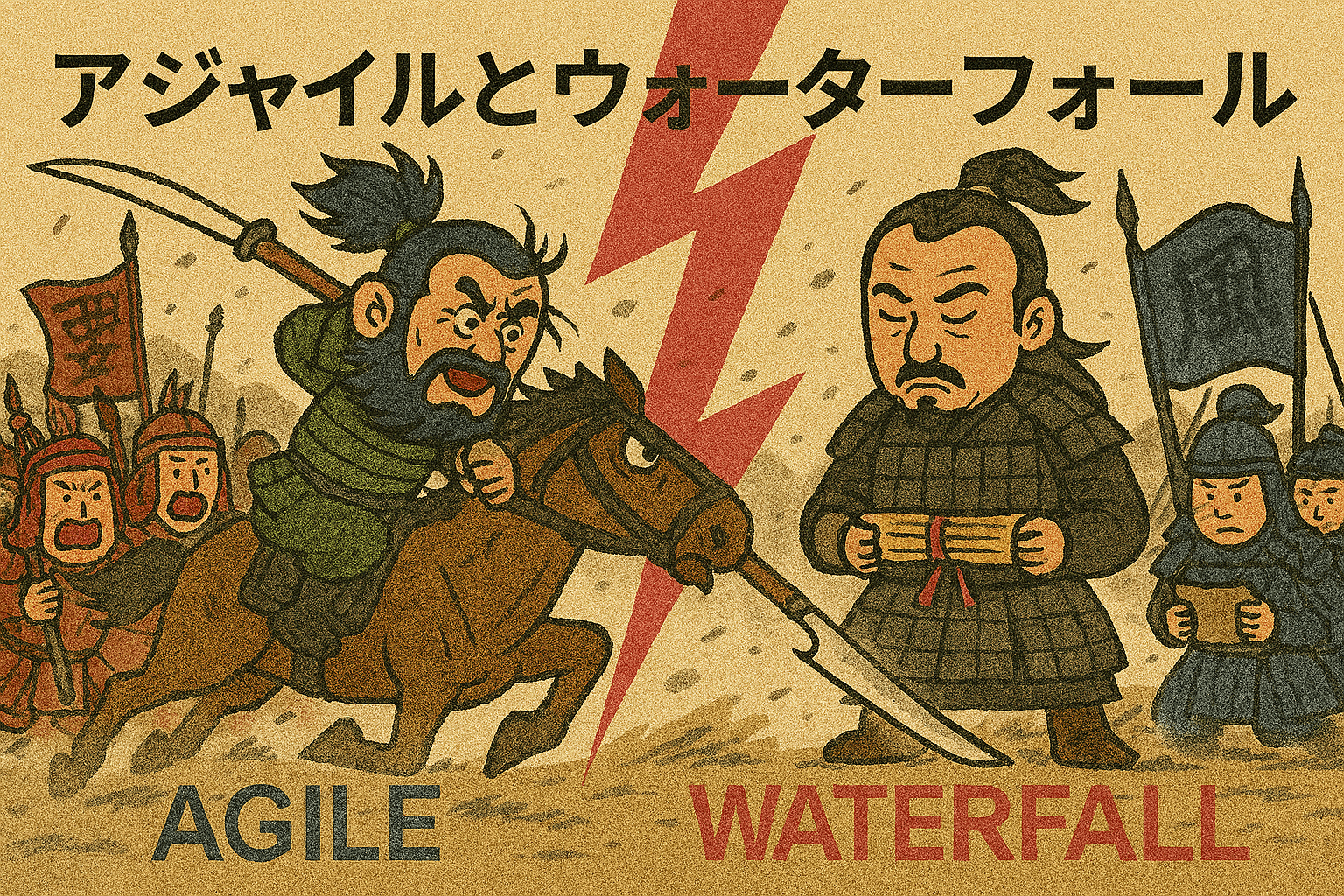
はじめに | アジャイルとウォーターフォール、相反するものなのか
ソフトウェア開発手法として知られるアジャイルとウォーターフォール。どちらが優れているかを論じる前に大切なのは、開発プロジェクトの規模やマネージャーの特性によって向き不向きが異なるという視点です。本稿ではまず開発規模、次にマネージャーのタイプから両者を整理し、最後にマンガ「キングダム」の登場人物になぞらえて考えてみます。
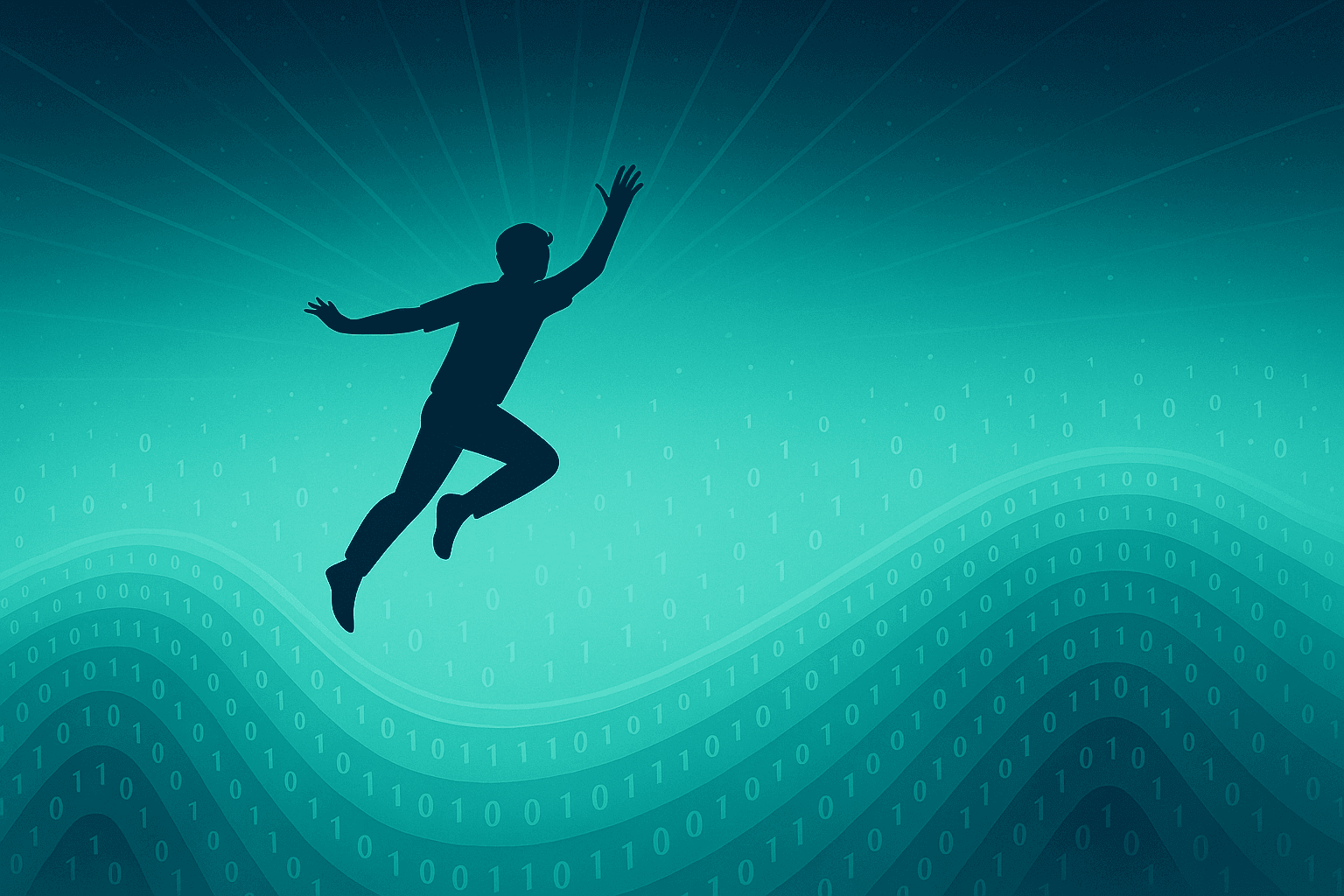
コラム:データの読み方
データ駆動、データを基にした意思決定。。。
古くはAlibabaやSpotifyが得意としてきました。最近はラーメンの山岡家も活用しているデータ。
現場にいるとこのデータの読み方がいまいち苦手な方が多くいらっしゃいます。
私自身まだ「AI」という言葉がここまで浸透する前に自然言語ベースのレコメンドエンジンを武器として、おすすめ記事のCTRを50%上昇させた経験があります。
データとは何か一緒に考えていきましょう
広告
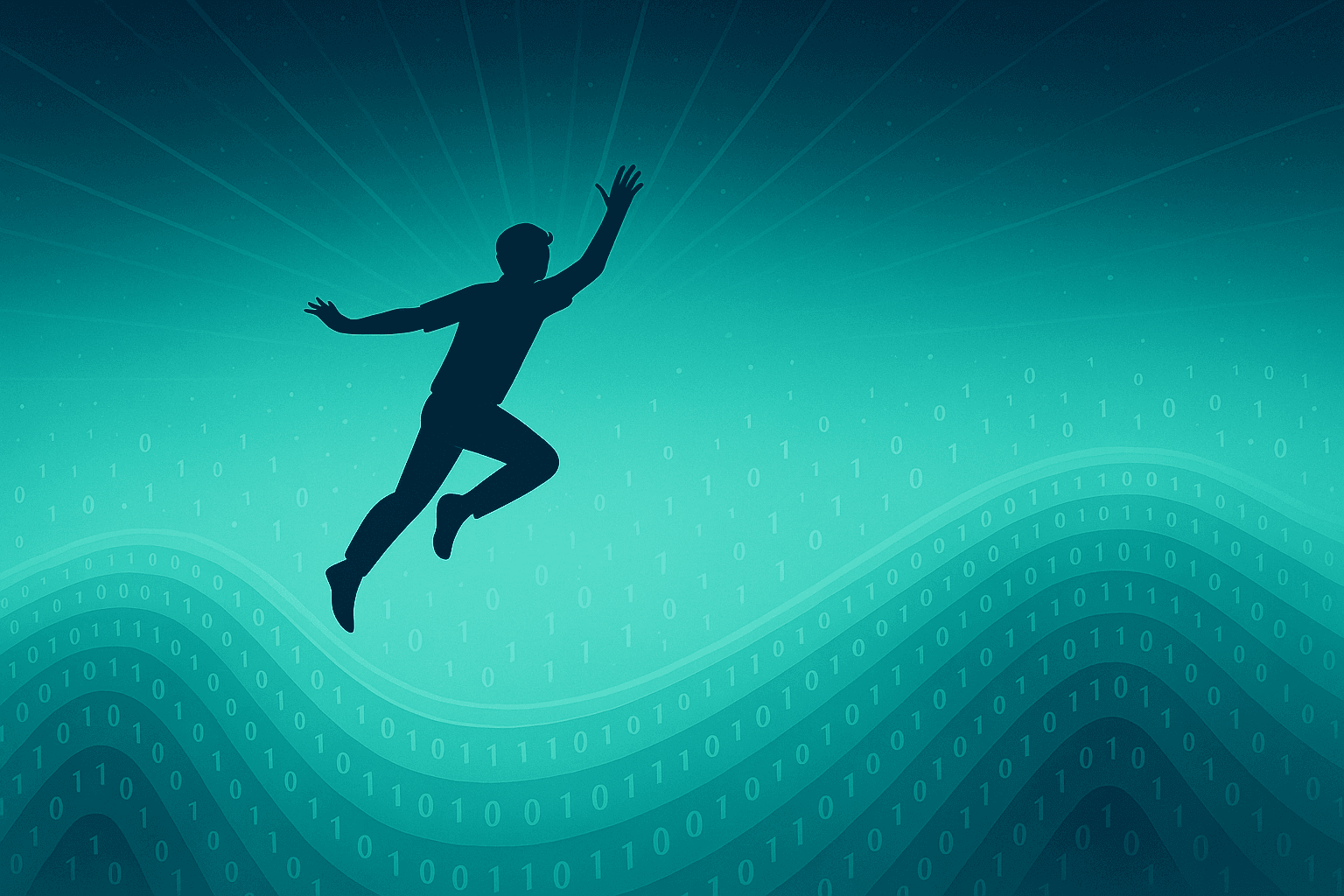
コラム:データの読み方
データ駆動、データを基にした意思決定。。。
古くはAlibabaやSpotifyが得意としてきました。最近はラーメンの山岡家も活用しているデータ。
現場にいるとこのデータの読み方がいまいち苦手な方が多くいらっしゃいます。
私自身まだ「AI」という言葉がここまで浸透する前に自然言語ベースのレコメンドエンジンを武器として、おすすめ記事のCTRを50%上昇させた経験があります。
データとは何か一緒に考えていきましょう